ニュートリション・ジャーナル
 ここで学べること
ここで学べること※このページは、医療介護従事者向け情報です。
食支援が病院と在宅をつなぐ
摂食嚥下機能の低下があり、窒息、誤嚥、誤嚥性肺炎につながる可能性がある場合、病院側はQOLを向上させるため、リスクを回避して静脈栄養や胃瘻などの経管栄養を患者に勧めることが多い。一方、在宅医療の現場では、リスク回避よりも患者の想いが重要なファクターになることがある。
在宅患者と家族、支える在宅医療チーム。双方を取材する中で、「食支援の重要性」と「食べたい患者」の存在を通して、急性期病院と患者との間にある「溝」が浮き彫りになった。溝を埋めるものは、何なのか。口から食べることにこだわり続ける患者とその家族、食支援に取り組む在宅医療チームの中に、その糸口を見つける。
在宅で遭遇した疑問「本当に食べられないのか?」
― 口から食べる機能を守りたい ―
「胃瘻から栄養を摂っている患者さんの中には、『食べたい想いを持っているのに、食べてはいけない』と言われている患者がいる。『本当に、口から食べることができないのか?』と疑問を抱くことがあります」。そう語るのは、わたなべクリニック(大阪府吹田市)理事長・院長の渡辺克哉先生。
「僕自身、急性期医療に携わっていたときは"食支援"という言葉すら知らなかった。食に重きを置いた医療というのは、考えたことも出会ったこともありませんでした」。そう勤務医時代を振り返る渡辺先生は、在宅医になったばかりの頃、提携していた歯科医(摂食嚥下領域の専門家)と出会って、初めて嚥下内視鏡を教えてもらったという。
「―衝撃的でした。食べられる機能を持っていました。そのことをきっかけに、もしかすると、"禁食"がわずかに残る、食べる機能まで衰えさせるかもしれないと思うようになりました。頭をよぎった疑問と嚥下機能検査が私のターニングポイントになりました。食支援の必要性を痛感した瞬間でした」。
胃瘻はその適応が正しければ、確実な栄養投与のための良いルートであることは、医療者として十分に理解している。一方で、食べたい気持ちに応えたい、適切な栄養管理・介入をしたい、口から食べる機能を守りたい、という想いが渡辺先生を食支援に向かわせた。

渡辺克哉(わたなべ・かつや)
医療法人社団日翔会理事長/わたなべクリニック(大阪府吹田市)院長・生野愛和病院(大阪市生野区)理事長。一般居宅の核家族化が進む中、サ高住をベースに訪問診療をスタートした。医療と介護の連携を学ぶ講座「わたなべ在宅塾」も定期的に開催している
『死んでもいいから食べたい!』
鰻の皮で窒息した患者
ある時、渡辺先生が定期巡回で訪問していた患者が、鰻の皮で喉を詰まらせ救急搬送された。嚥下機能評価では経口摂取は危険と評価されており、胃瘻をつけていたが、患者自身は「元気になるためには食べなくては! 死んでもいいから食べたい!」と経口摂取をあきらめなかった。患者の家族は搬送先の救急の医師から「もう食べさせないでほしい。食べるから詰まらせるのだ」と叱責されたという。
渡辺先生は直談判に出向く。「急性期病院の医師の立場や想いもわかる。しかし、食事が生きる気力となっている人に『二度と食べるな』と言えるだろうか。『在宅医療チームが慎重に対応し、これからもどうにか食べさせてあげたい。また救急搬送されるかもしれませんが、どうか宜しくお願いします』と説得して帰ってきました」。
食べたい患者の「希望」に寄り添う
同クリニックの言語聴覚士(ST)・玉元良一先生に相談し、訪問指導に加わってもらう。「詰まらせた時の喉内部の写真を見て、皮が張り付かなければなんとかなるのでは、と考えました」。"誤嚥するのは仕方ない状況である"ことを前提に、できるだけ貼り付かないような食形態を管理栄養士に相談する。患者の口の中や嚥下機能を確認しつつ、その状態に合う嚥下食をオーダーメイドで用意したそうだ。
「訓練として、食べる様子を見ていると、とても喜んで食べ、ムセはしても、詰まらせたことはありませんでした」と玉元先生は言う。患者からは『焼き鳥がいい』、『ステーキが食べたい』、『おでんは大丈夫か』と訪問の度に、嬉々として次々にリクエストされたという。この食支援が、患者の生きる気力になっていたのだろう。
「誤嚥や窒息リスクのある患者に口から食べさせるのは、正直言って怖いですよ。怖いけれど、それが患者の希望だったら、在宅医療チームの全員が腹をくくろう、最終的な責任は在宅医である私がとるから、できるだけその希望に添っていこうと思っています」。そう言って渡辺先生は、豪快に笑う。

玉元良一(たまもと・りょういち)
わたなべクリニック・生野愛和病院言語聴覚士。
地域にも患者家族にもオープンな「わたなべ在宅塾」
訪問診療を始めた当時は、渡辺先生自身、わからないことだらけ。まずは自分が学ばなければと考えた。ならば在宅医療にかかわるスタッフが一堂に会して学べる場を作ろうと、「わたなべ在宅塾」を立ち上げる。共に考え、学び、共有し、広め、地域の活力を高めていくことが目的だ。現在も定期的に開催され、今、話題の講師を招いている。他にも、施設スタッフとのカンファレンスや勉強会も実施しているという。
病院の機能分化により、急性期病院のスタッフは退院患者のフォローが難しい。自分たちが送り出した患者の生活する地域で、在宅チームはどんなサポートをし、どんな課題を抱えているのか。そういう実情を知って退院支援に活かすため、急性期病院のスタッフの参加も歓迎とのこと。地域にも、患者家族にもオープンのため、江端さん一家も参加されている。

食べる楽しみを届けてくれた成形した"嚥下食"
食べたい想いと家族の不安
「地獄のような10年でした」。そう振り返る江端真澄さん。わたなべクリニックの訪問診療を受けている江端重夫さんの妻だ。傍らには娘の左恵子さん。
重夫さんは、1988年喉頭がん、2005年に下咽頭がんで食道再建術を受けている。二度目の手術後、縫合不全により6カ月も経鼻経管栄養が続いた。その後、咽頭頸部食道狭窄が発覚し、徐々に悪化、現在狭窄部位は内径2〜3mmほどになる。それ以上の大きさの固形物は嚥下できず、狭窄部を閉塞させ嚥下不全になる現状だ。
食事は、当初はすり鉢でつぶしたやわらか食。徐々に喉の状態にあわせてミキサー食(ペースト食)に移行。家族と同じ食事や重夫さん用に個別で作った食事を一食一食ペースト状にした後に、念のためガーゼで裏ごしをしてなめらかな状態にする手間は、毎日毎食のことだけに計り知れなかった。詰まらせるたびに病院へ行き、鉗子付咽頭ファイバーで摘出してもらうために受診をする負担も相当のものだ。「詰まるかもしれない...と毎食のように不安を感じていました」と語る左恵子さん。家族の不安とは裏腹に、重夫さんの食べることへの欲求は強い。それならば、本人の希望に沿って、食べさせてあげたい―真澄さんと左恵子さんは、日々、負担や不安を抱えながらも、口から食べてもらうことを目指していった。
どの食材なら食べられるのか、どう調理したら食べられるのか、当時は誰かに教えてもらえる状況ではなかった。暗闇の中を歩くように、試行錯誤をしながら、チャレンジし続ける毎日だった。
地獄のような10年から一転
手探りの中、2015年秋頃に、左恵子さんは "べたつき"が詰まる原因ではないかという仮説を立てた。情報収集の中で、食材にもともとあるべたつきを飲み込みやすくするには「とろみ材」が最適ではないかと考えた。病院の内視鏡検査で咽頭の映像を見たときに、とろみ材を使った食事は、喉への付着がないことを目の当たりにする。その後プロ専用のブレンダーを導入、嚥下食の専門書も手に入れ、とろみ材を使ったペースト状の嚥下食づくりにさらに力を入れるようになった。次第に摘出で病院を受診する機会が減ってきた。
またそんな頃に、"わたなべ在宅塾"の存在を知る。「医療従事者の方が参加する塾でしたが、患者家族として参加させていただき、はじめて食支援(在宅NST)について知りました。2016年5月から同クリニックの訪問診療を始め、医師、看護師、言語聴覚士、管理栄養士が、内科全般と食支援を診てくれることになり、同じ想いで歩んでくれる仲間ができたのです」。
さらに大きな転換となったのは、「口から食べることをあきらめていたあの人へ」と題したNHKカルチャー主催の『おうちでできるえんげ食』の一日講座だった。「2016年7月に参加したのをきっかけに、道が開けたのです。講師の先生(ニュートリー株式会社の管理栄養士)が、ゲル化材を使うとペースト状の食事が普通の食事と変わらない見た目に成形できることを教えてくださいました。しょうが焼きの嚥下食の調理実習を見たときは、驚きました! お父さんに昔と同じように普通の食事を作ってあげられる! そう意気込んで帰路に着いたのを鮮明に覚えています」と真澄さんは語る。

以降は、クリニックの訪問管理栄養士の指導で、成形できる嚥下食づくりに力を注ぐ日々が始まった。江端家への訪問栄養食事指導を担当しているのは、管理栄養士・村田味菜子先生だ。「村田先生の手ほどきを受けると、火をいれるタイミングやどんなテクスチャーが良いのか、計量の仕方、ゲル化材の計算の仕方など、日常的に、ゼリー食を作るコツを教えてもらえて助かります。目の前で教えてもらえると『大変!』という想いが吹き飛んで『作れる!やれる!』という気持ちになるんです。成功体験が、嚥下食のメニューを増やしてくれます。本人の食べたいメニューをさらに増やしていきたいと思います」と左恵子さんは意気込む。成形できる「嚥下食」が、家族に食べる楽しみをもたらしてくれた。皆、希望を胸に前向きな心持ちでいる。
「2016年5月から江端さんの訪問栄養食事指導を担当していますが、家族の経口摂取への努力の結果、江端さんの1日平均栄養量は1600~1800kcalを維持でき、体重も安定しています。Alb4.0以上、血糖も安定しています。検査値はあくまで参考とし、まずは美味しく食べて頂くこと、そして元気になって頂くことが大切です。美味しい食事を栄養につなげることが栄養士の役割です。その人に合った嚥下食を、患者・家族と一緒になって考えなければなりません」と、医学的・栄養学的視点からの食事指導の重要性に触れる村田先生。
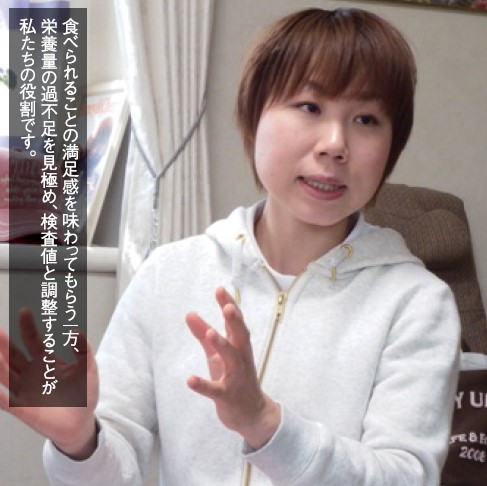
村田味菜子(むらた・みなこ)
わたなべクリニック・生野愛和病院管理栄養士。
在宅で診察や嚥下内視鏡検査(大阪大学大学院歯学研究科顎口腔機能治療学教室 野原幹司准教授による)を受け、かみ合わせの良い義歯を入れたことで重夫さんの嚥下機能が改善。初孫にも恵まれ、誕生日には三世代一緒のテーブルで同じ食事を共にしたいとの想いから、嚥下食のロールケーキを制作した真澄さんと左恵子さん。そのレシピは全国嚥下食レシピコンテストで大賞を受賞した。あの地獄のような10年間がいま劇的に変わった。
「今は在宅医療の環境が整い、摂食嚥下障害、嚥下食についての情報も以前より得られやすくなっています。かつての私たちのように嚥下障害に困っている人がいれば、少しでも早く新しい情報にアクセスしてほしい。今は、食支援のプロフェショナルがいる時代。未来は変えられると思います」と娘の左恵子さん。母娘の愛情と工夫に支えられ、嚥下障害を持つ重夫さんは、今日も真澄さんと左恵子さんお手製の嚥下食を楽しんでいる。

在宅での食支援は"最適化"がポイント
家族が"食べること"に固執しすぎるケースも
一方、患者本人が、食べることをストレスや苦痛に感じているのに、家族が食べることに固執している場合もある。
「家族には、"食べさせられた満足感"と"食べることにこだわらず楽しく過ごすこと"のどちらを選びますか? という話をします。必ずしも『食べること=楽しみ』とはならないケースがあります。説明をしてもなお、食べることを最後の希望と考えている家族もいる。そういう方には、そばにいて話しかけることや、暖かな手でさすってあげること、そんな楽しみもあると思うよ、と食べること以外の楽しみを探す道も示すよう、心掛けています。伝え方は、難しいですけどね」と玉元先生は語る。
食べられない現実を徐々に受け入れてもらえるように、段階を踏んでの対話を、患者、家族、医療チームが二人三脚で行う。「とはいっても、食べる機会は作るようにしています。"チャレンジをしたけれど、うまくいかなかったこと"と"チャレンジもさせてもらえなかったこと"は、患者や家族の受け止め方に大きな違いがあります。家族が『何もできなかった』と自身を責めて、後悔を引きずったまま生きることは、患者にとっても不本意でしょうから」と、その視線は患者にも、家族にも等しく注がれている。
「リハビリの役割は、一言でいうと"最適化する"ことですから、終末期、亡くなる直前まで続きます。在宅での食支援において、病状が安定している時は食べることが最適であっても、終末期にはそうではないかもしれません。その時その時で、生活環境に合わせて、何を最適とするのか、それを探していくんです。これは患者さんとのやり取りを何度も何度も繰り返してやっと実感したことです」。その言葉には説得力があった。
病院側は患者の生活を想像しゴールの設定を
「在宅医療チームの仕事は、食支援を通じて、治療が必要であれば、急性期病院をはじめとする専門領域につなげ、ケアが中心なのであれば、在宅医療チームの僕らがいろいろ工夫をして進んでいきます。
つまり患者の望むゴールに添って何ができるのかを考え、溝を埋めていくのが僕らの仕事です。医療者であれば、キュア(治療)も、ケア(支援)も、どちらも提供できなければいけません。正しい判断力とノウハウ、コミュ ニケーションツールなど、幅広い情報とネットワークを持っていることが大事なんだと思います」と語る渡辺先生。
「病院側の目指すゴールは、患者を治し、退院させること。患者側にとって退院はリスタートで、自分の一生を全うすることがゴール。退院させる病院側が退院後の患者の生活を想像し、視野をあとほんの少し広げてくれたなら、病院側と在宅医療側がスムーズに連携できるようになる。病院側の目指すゴールが、例えば"肺炎を治す"から"肺炎を治して家でご飯を食べられるようにする"になれば、医療の質が向上するはずです」と熱く語る。 リスクがある中で、何ができるか判断を積み重ねていく在宅医療。その場で取り組まれる食支援は、病院と「食べたい想い」を抱えた患者の双方をつなげ、溝を埋める役割を担っているかもしれない。

おうちでできるえんげ食Cooking
江端家では、重夫さんのために、成形した嚥下食を手作りしている。 食事は毎日のこと。日々の生活に取り入れるには、無理をしないことがポイントだ。

回答者:左から奥様の真澄さん、娘の左恵子さん
Q1 どのように嚥下食を作っているか、具体的に教えてください。
A1 家族と同じ食事を嚥下食にしたり、夫用に個別で作ったりしています。
家族用のメニューであれば、コストや手間の面で負担にならないのでおすすめです。その場合は、食事をペースト状にして、とろみ材「ソフティアS」を入れる調理法ですね。例えば、カレーやシチュー、麻婆豆腐、野菜の炊き合わせ、コロッケ、ポテトサラダなどがメニューです。
夫の場合、基本の食形態がペースト状なので、なめらかなペーストを作るためにミキサーが必要です。やわらか食を召し上がられる方であれば、圧力鍋などが便利ですよね。在宅介護での食事づくりも、病院や施設と同じように、道具はプロ用を用意しておくことをおすすめします。かなり調理がラクになり楽しくできます。毎日、毎食のことですから、道具はかなり重要です。(真澄)

Q2 毎食、ゼリー状の成形した嚥下食を作っているのですか?
A2 成形した嚥下食を作るのは、時々です。
本人が喜ぶメニューを意識して作っています。特に、オムライスは喜びます。本人の思い入れがあるメニューを成形していますね。キャラ弁など、流行のものも取り入れています。(真澄)

Q3 嚥下食のレシピは、どのようにして考えていますか?
A3 まずは、本人の食べたい想いや思い出などを最優先に考えますね。
実際に作るときは、書籍「おうちでできるえんげ食」を参考にしたり、訪問管理栄養士の村田先生に相談し、食材の量やゲル化材の添加量を調整しています。 また、テレビや雑誌を見て、家族が作ってみたい! というものも、チャレンジして作っています。(真澄)
Q4 成形した嚥下食レシピは何種類ありますか?
A4 うどん、蕎麦など、20種類ぐらいはあります。
基本ができれば、バリエーションが広がります。うどんであれば、カレーうどん、あんかけうどんもできます。うどんが作れるようになれば、蕎麦も同様にメニューを広げていけますね。
ゲル化材は、スタンダードタイプ、お粥に使いやすいタイプなどを使い分けています。お粥を作るときは、強力なミキサーで粉砕した白米や雑穀にゲル化材を加えてお粥ミキサーゼリーを作っています。ニュートリー社製のゲル化材を使っていますが、いつ作っても固さが一定で、味も美味しいですよ!
今週は、管理栄養士の村田先生にトンカツの作り方を教えていただきます。先日はエビチリを作りました。本人が嚥下障害になる前に、好んで食べていたものを成形できると、かなり食が進みます。あっという間に食べてしまいますよ。(左恵子)
ミキサー食に「ゲル化材」を加え 加熱すれば、成形した「嚥下食」に。
飲み込みが困難な人は、ペースト状のミキサー食を食べている場合が多いと思います。成形した「嚥下食」は、ペースト状のミキサー食にひと手間を加え、飲み込みに配慮しつつも、普通食の見た目に近づけた食事です。
ひと手間とは、ペースト状のミキサー食に「ゲル化材」を加えて加熱する工程のこと。この工程により、ゼリー状の成形した「嚥下食」を作ることができます。 ゼリーを作る、となると、ゼラチンや寒天を思い浮かべますが、飲み込みやすさの点では、ゼラチンも寒天も弱点があります。ゼラチンは、温度に弱いのが難点。一度ゼリー状に固めても常温で溶け出します。食事介助中に室温で溶けてしまったり、口の中で溶けてしまったり。一方、寒天は、まとまりにくく、バラつきやすいため、嚥下食の物性としては不向きです。

「飲み込みが困難な人」の介護をされる方向けに「飲み込み」や「嚥下食」にまつわる疑問と解決策をわかりやすくまとめた冊子「嚥下食まるわかりBOOK」。ニュートリーでは、栄養指導に使えるツールを充実させ、医療従事者の方々に提供しています。ぜひ、お気軽にお問い合わせください。

東邦大学医療センター大森病院栄養治療センター
"鷲澤尚宏先生に聞く"
 鷲澤尚宏(わしざわ・なおひろ)
鷲澤尚宏(わしざわ・なおひろ)
医学博士。東邦大学医学部臨床支援室教授。同医療センター大森病院栄養治療センター部長。消化器外科、栄養治療という専門分野を通して、日本における栄養サポートチーム(NST)の普及に初期より尽力。地域の医療・介護スタッフからも頼られる存在。
個々の患者さんで状況が異なるため人間愛が必須
「在宅医療に携わるようになってから、いろいろなものが見えてきた」とおっしゃる先生は大勢いらっしゃいます。急性期医療の世界で高度な知識と技術を身につけた先生方が患者のその後の生活を目の当たりにして、新たな発見をするのだと思います。
本来は、これらが並行して学べる環境が必要なのでしょう。教育機関の中には、医学知識を学ぶことと並行して医療現場の実態を体験させる教育に力を入れているところもありますが、医学教育の内容が膨大で、なかなかうまくいっていないようです。教科書の内容も最近では、ガイドラインなどを参考にして、エビデンスの明らかになった内容から順番に学ぶことが多いので、経験的なことをゆっくり体感しながら学べない現実もあります。
口から食べることの大切さと危険性を体感している専門領域の先生方は、裏付けとして、機能評価のエビデンス、食形態の研究、実践が必須なのです。
今回、登場する先生方は、ご自身の体験をワクワクする夢のある形で私たちにご教示くださいました。どうして、実践できたのか? 根底に「人間愛」があるからですね
本記事へのご意見、ご感想、身近な情報をお寄せください
発行: メディバンクス株式会社 ニュートリション・ジャーナル編集部
〒151-0051東京都渋谷区千駄ヶ谷3-4-23-203 TEL: 03-6447-1180 Mail: info@medi-banx.com
56_0057

